<高校生時代は学び一筋 1965年〜1967年>
毎朝、家を自転車で出て駅前の自転車預かり所に置き亀山駅7時20分発、阿漕駅まで25分間満員の機動車に乗り13分の地道を歩いて通学した。
亀山駅前には自転車預かり屋なる店が数軒あり多くの学生たちが利用していた。
同じ列車にはセントヨゼフの女子高生が乗っていたが育ちが違いすぎ自分たちとは縁遠かった。
下校時は1時間1本しかない列車に乗れるように地道を必死で走った。
乗り遅れると阿漕駅で暗くなるまでただ待つだけだった。
この頃はディーゼル機動車が主流だったがまだSLも健在だった。
朝には東京発の夜行列車「大和」が到着して去った後の糞尿まみれの線路を駅員が多量の水で洗浄していた。
当時の先生は、兵隊経験者もいて厳しかった。
専門教科では教師のレベル差がひどく不満だった。
工業高校の1年生を終えるころには電気学科は基本を習得し電検と呼ばれた電気主任技術者検定試験の予備試験に合格した。
2年生の夏に向けて授業内容を超えるレベルを猛勉強し本試験にチャレンジした。
すべてが記述式の狭き門だったがその冬に合格通知が届き最高の喜びだった。
高校2年生の秋には修学旅行で長崎、阿蘇山、別府のコースを旅した。
夜行列車の長い旅でようやく着いたのが長崎駅、永井隆博士の著書を読んだこともあり長崎原爆資料館は特に印象深かった。破壊された町並みの写真パネルは別世界のようだったが背景の山々は今と変わらず確かに20年前の姿だということを物語っていた。阿蘇から九重への広大な一帯は日本でないような感覚を覚え、もう一度見に行きたい場所だ。
<真空管時代の終焉に燃えた 1966年頃 17歳>
電子工学の分野では長く続いた真空管の時代が終わりトランジスタに代わろうとしていた。
1本50〜100円程度の中古球(真空管)を買い集め自作三昧の日々を楽しんだ。
技術の進歩の変わり目を実体験できる夢のある時代だった。
友達との付き合いも、特に望まず3年間ただ黙々と学んだ。
工業高校だからほぼ全員が大学へ進まず就職先を探していた。
名古屋の大手企業の面接を受けたら数人毎の集団面接で衣服を脱いで体格を見せるという今では考えられない審査であえなく撃沈した。当時は猫背でヘナヘナな体格だった。
次に受けたのは市中銀行だが面接で親戚縁者まで調べられてこれまた撃沈。
就活がすっかり嫌になりレベルを大幅に落として中小企業へ。これは簡単に採用となった。
<卒業そして社会人に 1967年(昭和42年)3月 18歳>
自動車産業は大きく羽ばたこうとしていた。
一部の階層の贅沢品でしかなかった自動車を庶民が持てる時代がやってきた。
隣の町の自動車部品メーカーに就職し目指していた電気技術者への道を歩むことになった。
<亀山事件と呼ばれる事故発生 1967年(昭和42年)7月19日>
JR加太駅の北側の集落で深夜民家に突然6千ボルトの電流が流れ込み何軒かが焼け一人が感電死した。
本来、配電線は変圧器が破損しても家庭の配線には150ボルト以上の電圧はかからない様、理論的にも実際的にも構成されている。ありえない事故で、全国の電力関係者を震撼させた。
調査が進むと事故発生以前から既にガイシ不良で高圧線が地面とつながっていた。
本来その時点で天神にある中部電力の変電所で保護装置が働き瞬時に安全装置により切り離されるはずが機能せず、あるいは機能をさせておらず、そのまま送電がされていた。
そこへ雷などの要因で高圧線から家庭向けの低圧線に電流が流れて何軒かの家の配線から火を噴く惨事となった。
この事故については関係者以外には広く知ることはなかったが事故後28年を経て1995年に発行された「文芸亀山」で摩枝あきら(ペンネーム)が「かわせみ」というタイトルの小説として発表した。
この人は既に故人であるがおそらく中部電力の関係者だと思う。
公にできなかった事実も多々あったと想像するが墓場まで持って行ったのだろう。
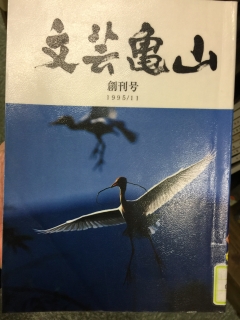 亀山事件を一般向けに初めて取り上げた文芸亀山
亀山事件を一般向けに初めて取り上げた文芸亀山
<やっとのことで持ち家となる 1969年(昭和44年) 20歳>
姉も高校を出るとOLとして社会に出て21歳で嫁ぎ我が家の家計も、ようやく余裕がでてきた。
市営住宅から持ち家へと準備を進めた。
近くに120坪の土地を買った。(坪1万円と当時としては高価な買い物だった)
父の退職金を合わせ300万円で家を建てようやく市営住宅住まいを終えることができた。
その後、高度経済成長により一気に物価が上昇し、持ち家は庶民から縁遠くなったのである。

平屋建てを建て、ようやく持ち家となった。
<若者らしい暮らしはしなかった>
当時の若い男性はマイカーを買い女性たちとドライブするのが大勢だった。
人と同じことをするのが嫌いなので、免許は取ったが車は買わず、スーパーカブで25歳まで通した。
成人式も出席せず日曜出勤して働いていた。
原風景としての鈴鹿の山をいつか自由に歩きたい願望は持っていたが、特に登山が趣味ではなかった。

社会人となりたての頃の入道岳登山
|
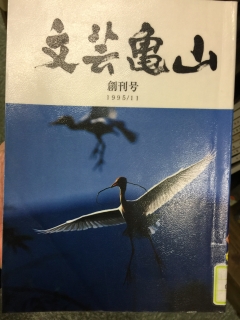 亀山事件を一般向けに初めて取り上げた文芸亀山
亀山事件を一般向けに初めて取り上げた文芸亀山
